|
「小さい泡のお話」

幕田研究室のオープンキャンパス特設ページへようこそ!
このページでは当研究室での研究を紹介しています。
またこのページは当学科3年生向けの研究紹介も兼ねています。
高校生は進学先選び・学科3年生は研究室選びの参考にしてください。
研究紹介動画(YouTubeでも公開中)
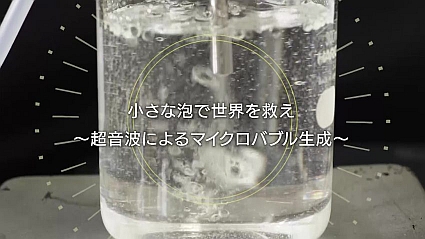
画像をクリックするとYouTubeの動画に移動します
模擬講義
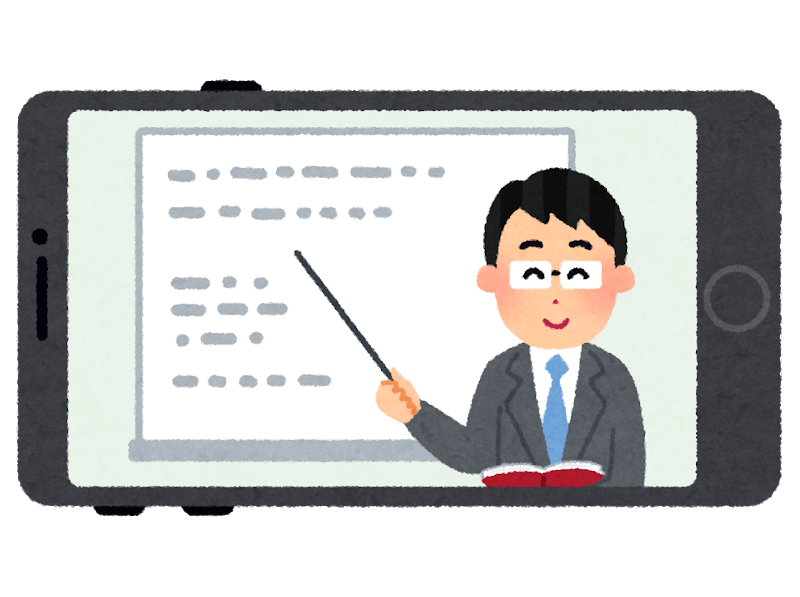
幕田教員による模擬講義の動画はこちら
(進学情報サイトの夢ナビのホームページに移動します。)
研究室の概要や主な研究は以下の動画もご参照ください。
(それぞれ約3分程度です)
1.研究室全体の紹介
2.マイクロバブル発生装置の開発
3.中空粒子の開発
4.食品への応用
5.蓄熱粒子の開発
6.ポーラス金属の開発
幕田研では、流体工学をベースとして、非常に小さな泡である“マイクロバブル”の研究を行っています。マイクロバブルは環境・医療・工業・農水産業など幅広い用途で有用であると注目を集めており、実際に効果を挙げている例が次々に報告されています。本研究室では、マイクロバブルの発生・特性・応用について研究しています。
○まず、マイクロバブルって何?
マイクロバブルは、読んで字のごとく「マイクロ(1μm=1/1000mm)」な大きさの「バブル(気泡)」のことです。ここでいうマイクロバブルは50μm以下の気泡のことを指します(ただし、研究者や用途によって定義は異なります)。
○普通のバブルと何が違う?
マイクロバブルが普通の皆さんが目にするバブルと違う点は何点かあります。その一つは体積当たりの表面積が大きい点です。同じ量の気体を液体中に吹き込んだとすれば、大きい気泡よりも小さい気泡の方が気体と液体が接する表面積が大きくなります。スイカを例にして考えてみましょう。スイカは切らなければ外側の縞々の緑の部分しか見えませんが、一回半分に切ると、美味しそうなスイカの赤い部分が見えるようになります。スイカを半分に切っただけですから当然体積は同じですので、見えた切り口の分だけ表面積が増えたことになります。さらにスイカを切ればまた切り口分だけ表面積が増えますから、細かく切れば切るほど表面積は大きくなります。これと同じで1個の大きい気泡が全部マイクロバブルになったとすれば、表面積は格段に増えることになる訳です。
他にも、浮力の影響が小さくなるので浮上する速度が遅い点、表面張力の影響によって形状がほぼ真球になる点やバブルの内部の圧力が高くなる点などもマイクロバブルの特徴です。
○どういうことに使えるの?
マイクロバブルは、先に少し触れたように体積あたり広い表面積を持っていますので、生物的・化学的な反応において気体を液体に溶解させる工程や、気泡の表面に汚れを付着させて取り除く過程などに有効とされています。また、大型船舶の底に気泡を流して船が受ける水の抵抗を減らす技術なども開発が進められています。近年では毛細血管を通過できる大きさの気泡を体内に導入して血液の流れを鮮明に見る超音波造影剤や、薬品を任意の位置まで運ぶドラッグデリバリーシステムの薬の運び手としての研究も進められています。
○それで、何を研究しているの?
現在行っているのは、超音波と針またはホーンを使って、20
mm以下のマイクロバブルをばらつきなく生成する技術や、マイクロバブルの周りに樹脂膜を形成させて作る中空カプセルの研究などです。最近では、血液中に導入が可能な医療用バブル(カプセル)の開発や、排熱を蓄えることの出来る蓄熱カプセル、マイクロバブルを含む発泡金属などの研究も行っています。詳しい内容はこちらのぺージにも記載していますが、わからないことがあれば遠慮なくお問い合わせください。
|

